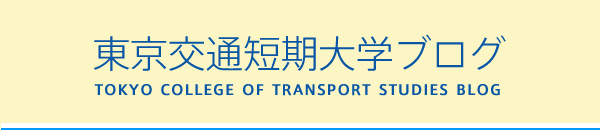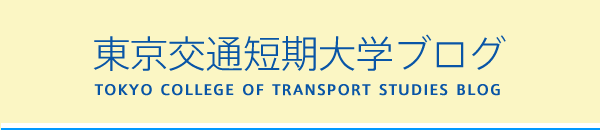鉄道総研見学
去る2月19日(水)、交通論ゼミの有志が、鉄道総研フェローで、一般財団法人研友社会長でもある垂水尚志氏にお招きいただき、国立市にある公益財団法人鉄道総合技術研究所(鉄道総研)国立研究所を見学してきました。

3月に卒業を控え、内定先交通事業者の事前研修などで全員の参加がかないませんでしたが、ゼミ生9名と担当教員の10名でお邪魔しました。
鉄道総研は、1907年に帝国鉄道庁鉄道調査所として創設されて以来、国内外の鉄道技術開発を常に先導してきた研究所です。安全でかつ高速に運行できる「新幹線」(高速鉄道)の技術は鉄道総研の前身である国鉄鉄道技術研究所が開発してきたものです。国鉄改革により、国鉄本社の技術開発部門と鉄道技術研究所などの業務を継承する法人として1987年に発足しました。
国立研究所は、東京ドーム4つ分という広大な敷地に、試験線の線路に囲まれるよう、実験設備や実験棟があります。この実験設備や実験棟の建物出入口近くには自転車が停められていて、職員の方々の移動には自転車が活躍しているそうです。
私たちは鉄道総研の説明VTRを拝見したのち、バスに乗り込み、最初に「車内快適性シミュレータ」に案内されました。その途中、緑が溢れる道路は「井深通り」と名づけられていて“IBUKA Street”の看板もあります。「井深」は、ソニーの創業者で鉄道総研の初代会長を務めた井深大(1908―97)氏にちなむもの。こういったところにも、技術開発のスピリッツを感じずにはいられません。
「車内快適性シミュレータ」は、振動や温度・湿度、騒音など列車内の環境要因を模擬的に発生させる装置で、巨大スクリーンに映し出される画像とシミュレータ装置が連動して動き、列車内を再現した装置内に座っていると、まるで本物の列車に乗っているかのよう。本学にも鉄道運転シミュレータがあり、「鉄道基礎」などで活用しています。当たり前ですが、こちらの装置がはるかに上の性能でした。
次に、非電化区間も走行できる電車「架線・バッテリーハイブリッド電車」に乗り込んで説明を受けました。このハイブリット電車は既に実用化されているものもあり、JR東日本のEV-E301系やEV-E801系、JR九州のBEC819系(DENCHA)がそれらにあたります。鉄道総研のハイブリッド電車は路面電車タイプで、路面電車タイプの蓄電池ハイブリッド電車が実用化されると、ライトレールやトラムから給電のための架線がなくなり、町並みがすっきりしたものになるでしょう。
さらに、震度7クラスの地震動を起こせる「大型振動試験装置」は、日本のような地震大国とも呼ばれる国で、地震動から高速鉄道を安全に速やかに停止させるためにも必要な模擬実験を繰り返し繰り返し行うための装置で、国内では防災科研のE-ディフェンスに並ぶ大きな装置だそうです。
実際の試験車輛を載せて最高速度500km/hまでの仮想走行試験ができる「車両試験装置」では、偶然にも試験が行われていないときだったため、回転する円形の「線路」を間近に拝見することもできました。最後に最多時間雨量300ミリの雨を再現できる「大型降雨実験装置」を拝見しました。この装置では、鉄道の盛り土をどう補強すればより降雨に強くなるのかを実験する装置で、私たちは実際に時間雨量300ミリの「豪雨」の中を歩かせてもらいました。2011年に新潟県内で観測した10分間雨量の最多記録が50ミリですから、この最多記録と並ぶ雨量を模擬体験できるのは貴重な経験でした。
広い研究所内をおよそ2時間半かけてご案内いただきました。しかし、見学している時間はあっと言う間で、もうこんな時間になってしまったというのが正直なところでした。
ご多用のところ、この見学にご協力いただきました鉄道総研職員の方々、またご紹介いただきました垂水会長には、この場をかりてあらためて御礼申し上げます。
後日、見学に参加したゼミ生から感想が寄せられました。
今回の鉄道総研の見学では、小学生の頃から抱いていた夢を叶えることができて、とても嬉しく思いました。私の「鉄道総研に入る(仕事をする)」という夢は高校受験で某高校に落ちたことがきっかけで叶わぬものとなってしまったためです。見学した研究は、どれも小学生の頃に記事で読んで「鉄道総研に入りたい」と思うきっかけとなった研究で、今回はこれらの研究をより近い場所で見学することができ、感無量でした。また、「モノづくりを通じて誰かを喜ばせたい」という当時の純粋な気持ちを思い出させてくれた貴重な経験でもありました。今回の見学に関係するすべての方々には感謝しかありません。
鉄道総研は、我々が想像できないようなデジタル化を駆使した近未来の研究を行なっているイメージが強かった。実際に見学させていただくと、視覚や振動によってあたかも自分が電車に乗っているような気分にさせて乗り心地を改良する装置など、大規模かつ簡単には仕組みが理解できないものが多かった。しかし、雨量計は2つの容器が水の重さにより交互に転倒する回数を数えて雨量を測るという構造が簡単に理解でき、また、アナログ的な要素があると思った。大規模な装置を用いた実験により技術革新や利便性の向上につながることも多いと思うが、案外簡単な構造であっても実社会で活躍している技術があることを学んだ。
座学で学んでいくこともとても大切なのですが、こういったさまざまな現場で学ぶことも、それに並ぶほど大切なことだと、引率して痛感したものです。

※写真掲載は事前に鉄道総合技術研究所にご了承いただいております
2026.01.27 2025年9月に観光庁長官が実施する国内旅行業務取扱管理者試験が実施されました
2026.01.25 交通文化論ゼミの合宿
2026.01.01 謹んで新春のお慶びを申し上げます
2025.12.20 『鉄道業界就職ガイドブック2027』に本学が掲載されました
2025.12.15 来年の干支・「ウマ」がつく駅をめぐる
2025.12.10 学生による学生のための私鉄特化型の就活セミナー開催!
2025.12.05 企業の業務体験学習と発表会
2025.12.01 2026年度入学予定者向け入学前講座を実施しました
2025.11.29 関東鉄道を存分に楽しもう!-「交通見学会」in 2025-
2025.11.27 本学卒業生の山中真ノ介先生にご講演いただきました!
2025.11.26 【交通情報論ゼミ合宿③】名古屋&リニア鉄道館
2025.11.25 【交通情報論ゼミ合宿②】大阪環状線&JRゆめ咲線で行くユニバーサル・スタジオ・ジャパン!?
2025.11.24 【交通情報論ゼミ合宿①】新幹線で大阪へ!観光から研究発表まで大充実の1日!
2025.11.22 本学独自の特待奨学生制度 授与式を行いました
2025.11.19 文部科学大臣認定の数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)の修了証授与式を執り行いました!
2025.11.17 文部科学大臣認定の数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)に認定されました!
2025.10.27 フィナーレは祝砲とともに 鉄道200周年記念イベント潜入記 ③
2025.10.15 200年前と同じあの場所で… ロコモーション号はダーリントンへ 鉄道200周年記念イベント潜入記②
2025.10.10 東交祭2025を開催しました!
2025.10.06 伝説のあの機関車がついに走る…! - 鉄道200周年記念イベント潜入記① -
2025.09.06 高知往復鉄道移動、帰りはサンライズ!
2025.08.12 今年も「国内旅行業務取扱管理者試験」の夏期講習が始まりました!
2025.08.05 南東北の小さな旅
2025.07.26 地域の足を守る 特別教養講座「地方鉄道の現状とダイヤ作成について」開催
2025.07.23 AED講習と消火栓放水訓練に参加してきました
2025.07.16 2025年度 最新内定状況!(2025年7月15日)
2025.06.26 キハ10保存会の活動に参加!
2025.06.16 学外レクリエーション「JR東日本”都区内パス”を利用してのオリエンテーリング」を実施しました
2025.06.10 東武鉄道に魅せられた学生と共に進路決定のご挨拶へ!—杉戸高校訪問記—
2025.06.02 ボウリング部の活動🎳 池袋ロサボウルでボウリング!
2025.05.26 「交通文化論ゼミ」で「武蔵野鉄道 開通110年周年」展を見に行きました
2025.05.13 「歴史学A」で祭りの見学に行きました!
2025.05.07 『鉄道百五十年史』贈呈式挙行
2025.04.08 日本貨物鉄道株式会社 隅田川駅見学 Vol.2
2025.04.01 日本貨物鉄道株式会社 隅田川駅見学 Vol.1
2025.01.28 ニュース時事能力検定試験1級に合格しました
2025.01.06 新年のご挨拶
2024.12.25 専門ゼミ発表会が開催されました
2024.12.05 「巳・蛇」がつく交通スポットをめぐる
2024.11.12 交通見学会 ~小田急電鉄 喜多見電車基地&小田急バス 登戸営業所~
2024.11.04 卒業生が講師として「ご存じですか?【駅運転】のお仕事。」を講義
2024.10.03 交通文化論ゼミの合宿
2024.09.25 入試がいよいよ始まりました!
2024.08.06 旅取(国内旅行業務取扱管理者)試験対策夏期講習が始まりました!
2024.07.30 JTB様に内定いただきました
2024.07.23 2024年度(令和6年度)特待奨学生証書授与式が行われました
2024.07.09 AED講習会に参加しました
2024.06.29 本学卒業生の小澤梓先生にご講演いただきました!
2024.06.20 学外レクリエーション「東京メトロ24時間券を利用してのオリエンテーリング」を実施しました
2024.06.15 2024年度 最新内定状況!(2024年6月10日)
2024.06.10 本学卒業生の渡邊俊介先生にご講演いただきました!
2024.06.03 日本語検定対策講座が始まりました!
2024.05.27 B Sフジ「レッツ・トレ活」の撮影が行われました♪
2024.03.18 櫻井 寛 写真展「列車で行こう!The Railway World」開催
2024.03.13 学生会主催で就職活動セミナーを開催しました
2024.03.06 鉄道の安全運行への努力に触れる -小田急相模大野車両基地見学-
2024.02.28 鉄道貨物を支える人々に密着 -JR貨物 隅田川駅見学-
2024.02.22 在学生向けの鉄道運転シミュレータ体験会を実施しました
2024.02.16 学生論文集の表紙を飾る写真が決定しました!
2024.02.05 「辰・龍・竜」がつく「バス停」をめぐる
2024.02.02 専門ゼミ発表会が開催されました
2024.01.26 四年制大学から就職、そして本学入学へ
2024.01.20 新年のご挨拶
2023.12.19 「学外活動」で王子神社のお祭りと東大博物館へ!
2023.12.06 平日キャンパス見学会を再開いたします
2023.12.03 鉄道会社による「ゲン担ぎ」
2023.11.14 引退前のVSEに乗ってみた!―「交通見学会」in 2023―
2023.10.16 首都圏の短編成列車をめぐる3:下町遊歩編
2023.10.07 東交祭(2023)を開催しました
2023.09.10 首都圏の短編成列車をめぐる2:多摩迷走編
2023.08.30 本所防災館体験ツアーに参加しました
2023.08.17 旅取夏期講習が始まりました!
2023.08.03 首都圏の短編成列車をめぐる1
2023.07.24 2023年度(令和5年度)特待奨学生証書授与式が行われました
2023.07.12 学園主催のAED講習に参加しました
2023.06.05 学外レクリエーション「JR東日本都区内パスを利用してのオリエンテーリング」を実施しました
2023.05.18 『鉄道ダイヤ情報』に卒業生が掲載されました!
2023.05.11 旅行業務取扱管理者試験に合格しました!
2023.05.02 減りゆく「頭端式ホーム」を訪ねて
2023.04.17 祝開業 東急新横浜線!
2023.02.10 JR貨物のインターンシップで隅田川駅・隅田川機関区へ!
2023.01.19 専門ゼミ発表会が開催されました
2023.01.11 本学が「鉄道業界就職ガイドブック2024」に掲載されました
2022.12.17 初めてのひとり暮らしの強い味方!学生マンションのご紹介
2022.12.11 創立70周年記念式典
2022.12.03 ミニ・オープンキャンパスを実施しました
2022.11.07 交通見学会を実施しました!
2022.10.18 日本語検定 団体表彰 東京書籍賞・優秀賞受賞にあたって
2022.10.11 本学卒業生の卒業論文が引用されました!
2022.10.02 今年も東交祭を開催しました!
2022.09.29 「鉄道史ゼミ」日帰りゼミ旅行!!
2022.09.14 JR貨物の駅長OBに直撃インタビュー第二弾
2022.09.10 池袋防災館体験ツアーに参加しました
2022.09.02 「鉄道ゼミ」に出張模擬授業&説明会
2022.08.12 旅取夏期講習が始まりました
2022.08.08 2022年度(令和4年度)特待奨学生証書授与式が行われました
2022.08.01 新型コロナウィルスワクチンの学内接種を実施
2022.07.21 JR貨物の駅長OBに直撃インタビュー
2022.07.13 学園主催のAED講習に参加しました
2022.06.26 学外活動で「沖縄復帰50 年」企画展へ
2022.06.20 オープンキャンパスへ行ってみよう
2022.05.24 東京メトロ24時間券で学外レクリエーション
2022.05.04 卒業生が特別教養講座講師に
2022.04.25 卒業生との座談会(キャリア支援室主催)
2022.04.22 鉄道会社で働くために役立つ資格とは
2022.04.01 学長挨拶
2022.03.31 名誉教授称号授与式が行われました
2022.03.30 学長退任のご挨拶
2022.03.14 本学が「鉄道業界就職ガイドブック2023」に掲載されました
2022.02.14 さようなら、京急パタパタ
2022.01.17 大学入学共通テストで鉄道の時刻表
2022.01.06 新年のご挨拶
2021.12.24 鉄道博物館で夜間貸切イベント
2021.11.30 ゼミ旅行 茨城空港見学と関東鉄道車両基地見学
2021.11.29 2021年度最新内定状況
2021.11.20 喜多見車両基地から貸切ロマンスカーで出発
2021.11.16 湯田先生がラジオ番組にゲスト出演されました
2021.10.24 「幸福の招き猫電車」と10,000匹の招き猫 (=^ェ^=)
2021.09.27 2日間の東交祭
2021.09.15 オープンキャンパスでシミュレータ体験
2021.08.05 2021オープンキャンパス開催
2021.06.04 資格取得者の紹介&資格の種類
2021.05.28 毎月1日はモチベーションア〜ップ
2021.03.16 新幹線のおなまえっ
2021.02.01 交通英語って何だろう
2021.01.11 「今だからこそできること」を考えよう
2021.01.06 新年のご挨拶
2020.11.16 交通見学会で周遊クルーズ
2020.10.14 東交祭を開催しました
2020.09.11 AERAMOOK「就職力で選ぶ大学2021」短期大学GUIDE BOOKに掲載
2020.09.02 保護者向け説明会を実施しました
2020.09.01 第1回オープンキャンパス開催
2020.07.18 日本の鉄道車両の大活躍inジャカルタ
2020.06.09 オンライン授業がスタートしてから1ヶ月が経ちました
2020.04.20 鉄道偉人の「掃苔」
2020.03.10 鉄道研究部の野外活動(フィールドワーク)
2020.03.02 鉄道総研見学
2020.02.18 交通・観光業界 女子高校生向け座談会 開催
2020.01.28 初詣と鉄道
2020.01.21 「交通・観光業界 女子高生向け座談会」を開催します
2020.01.14 本学学生が情報セキュリティマネジメント試験に合格しました
2020.01.06 新年のご挨拶
2019.12.10 国土交通省職員研修の講師を務めました
2019.11.26 都電荒川線貸し切りツアー
2019.11.09 10月30日に交通見学会を実施しました
2019.10.22 交通論ゼミ ゼミ合宿2019(3日目)
2019.10.14 交通論ゼミ ゼミ合宿2019(2日目)
2019.10.07 交通論ゼミ ゼミ合宿2019(1日目)
2019.10.06 交通論ゼミ ゼミ合宿2019
2019.09.30 東交祭を開催しました
2019.09.24 交通判例分析ゼミ夏期合宿
2019.09.17 ゼミ合宿報告(労働法ゼミ)
2019.09.10 小鉄日記3「ちかはく満喫」編
2019.09.02 第2回オープンキャンパスが開催されました
2019.08.19 本学の指定学生寮に見学に行きました
2019.08.13 「鉄道模型コンテスト2019」に参加しました
2019.08.10 2019年度 就職内定状況
2019.08.06 2018年度資格取得状況
2019.07.30 東京オリンピック・パラリンピックまであと1年
2019.07.20 第1回オープンキャンパスが開催されました
2019.07.13 オープンキャンパス開催のお知らせ
2019.06.26 令和元年度 春の叙勲報告
2019.06.25 歴史の博物館の見学
2019.06.20 短大のうちわが完成しました
2019.06.11 学外レクリエーション
2019.06.04 寝台列車の生きる道
2019.05.28 ガイドブックが完成しました
2019.05.21 平成から令和への「ゴールデンウィーク」
2019.05.13 本学の歴史について
2019.05.03 今年度最初の体験入学会が実施されました
2019.04.21 小鉄日記2「もう一つの学校」編
2019.04.14 東京交通短期大学にたどり着くキーワード
2019.04.04 小鉄日記
2019.04.01 本学卒業生いすみ鉄道社長に就任
2019.02.16 アクセス
2019.01.29 ご挨拶